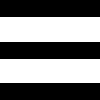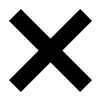フランスの会社からインドネシアのジャカルタに派遣されていた夫は、パリでの2か月のヴァカンスの後にインドネシアに1人で発った。私は約3週間後の出産のためにパリに残った。無事に出産後子どもと一緒にインドネシアに行く予定であった。子どものいる日仏カップルの友人がいたので、大きくなったお腹でおしゃべりに行ったりしてはゆっくりと時間を過ごしていた。「案ずるより産むがやすし」と日本の言葉通りに、「余計な心配事を考えず出産のその日まで楽しく過ごそう、そうすればおなかの子も喜ぶのではないか」と、いつも楽天的な思考で何事も飛び越えてきた私は、自分勝手にそう考えていたのだ。
ある日の夜中、ベッドがびちゃびちゃでおしっこでもしたのかと驚いて起きたが「ああこれがもしかしたら早期破水かも」と思って友人に電話をした。友人はタクシーですぐに来てくれて、そのまま私の通っていた産科の病院へ直行した。安静にしていたが陣痛が激しくなったので手術室に運ばれた。私は苦しくてうなっていたが、看護士や助産士はまだ時間がかかると思ったらしく私を一人にして次の部屋へと行ってしまった。私の部屋のドアを開けっぱなしのままで。開いたままのドアの方からは隣の妊婦の悲鳴が聞こえたり、家族が駆け付けたりしていた。私は苦しい中で思った。「なぜドアを開けっぱなし?関係ない人もちらちらと私のアラレモナイ状態が見えるではないか……」と。
その日は絶食させられていたが、ものすごい空腹感でがまんができない状態だった。他の人に持ってゆく配膳係のマダムに情けない声で「お願いそのパン一かけらでいいからちょうだい、お腹すいて死にそうー」「いいえダメです」「ほんの一口でいいからー」と、まるで飢餓難民のようだった。配膳係のマダムは私の憐れな声に折れて、ほんの一口のパンをくれたのだった。私にとってはまさに「命のパン」だった。
その後何時間たったか分からなかったが、意識がもうろうとしていた時に友人の声が聞こえた。「ハンサムな男の子よ。今保育器に入っているわよ」。「あー生まれたのだ」と思いまた私は寝てしまった。疲れ果ててしばらくうとうとしていると、耳元でうるさく泣く赤ん坊の声が聞こえた。横を向くと小さなベッドで赤ん坊が歯のない大口を開けてぎゃーぎゃー泣いているではないか。「これが私の子なんだ!」と知った。

息子の誕生直後(友人の夫が撮影)

誕生9日目(自宅にて筆者撮影)

息子誕生から6日目退院の日(母子専門のプロの写真家が病院に撮影にきた)
(つづく)