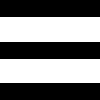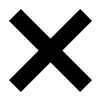当時(約35~40年前)のパリは、まだ、訪れる日本人は少なかった。パリでもなかなか会えない日本人だったが、ナイジェリアのカノの町を歩いているときに偶然に日本人の男性たちに出会った。
奇跡的な出来事のように「ぜひ私たちの住む家に来てください。ここで日本人女性と会うなんて!」と感激して招待してくれた。彼らは某会社の駐在員として滞在していたのだった。何ヵ月か後、夫(フランス人)と一緒に訪ねることにした。
何しろここには住所というものがない。もちろん私たちの居住区もそんなものはなく、手紙を受け取るにはカノの町に会社の私書箱があるだけである。家を探すには何キロ先のバオバブの木の何番目を右折、何キロ先の大きな石を左折という説明などで尋ねる。
日本人が住む村の名前を告げ、村人に聞きながら彼らの居住する家に辿り着いた。4人の日本人男性たちが一緒に住んでいて、ボーイに和食らしきものを教えて料理した美味しいご馳走をいただいた。まさに日本の「宴会」がはじまったのだった。私も思いっきり日本語を話すことができるので嬉しかった。
「カラオケをしましょう」と言われたが、私はこの「カラオケ」とはどういうものだった分からなかった。私が最初に日本を発ったのが、1974年頃で、記憶にはないコトバであったからだ。しかし、すぐ理解できた。室内に「カラオケ」の大型の機械が設置してあった。日本で急激に流行りはじめた「カラオケ」を、娯楽が何もない砂漠の村に持ち込んでいた。「あなたも歌って下さい」と促され、うるおぼえの「カスバの女」や日本の歌を下手ながらも歌ったら、日本人男性たちは大喜びしてくれた。
壁には日章旗が張ってあり、日本の会社の人たちの寄せ書きが書いてあった。それを見たら、私はまるで遠い地の果ての戦場に慰問に行った歌手になったような思いが浮かんだものである。夫も「仕方がない」という顔でアルザス語(夫はアルザス地方で生まれ少年時代を過ごした)でその地方の艶歌を歌ったが、誰も分らないからよいのであった。楽しい「宴会」に1年間のストック用の酒やウイスキーなどを、その晩で飲み干してしまったようだ。
彼らは毛布生産の製作指導のためにアフリカの僻地に来ていたのだった。「なぜ、ここで毛布が必要なの?」と質問すると、サハラは寒暖の差が激しく夜は冷え込むので、毛布だとたためばどこへでもでも持っていけるし、敷けば良い敷物になるので、今までになかった生活のための貴重な必需品となったという。
夫とお礼を言っての帰り道「あの人たち、残りの日々をアルコ-ルなしで過ごさなくてはいけないから、今頃後悔しているのでは?」と、少し心配しながら夫と話した。
夕方になった帰り道、カノの町の近くを通り私たちの住む村へと車を走らせていたら、あちらこちらから黒い煙と火の手が上がっているのが見えた。

筆者(左)と夫アンリ―(右)と日本人駐在員(中央)

日章旗を背景に「カラオケ」を歌う筆者と日本人駐在員

パルのモームパーティーのようにみんなでダンスを楽しむ
(つづく)