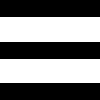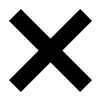今年も秋田は熊の日々である。マタギの阿仁地区リンゴ畑には今年1頭も出ないのに秋田市内の住宅街では生徒の通学路がケモノ道になったらしい。大人たちが付き添っているものの非武装丸腰の同行がどんな役に立つのだろうか。繁華街の倉庫に侵入し民家に押し入り、私が通う近所のスポーツジム近辺にも出たため自動ドアはスイッチを切った。熊が通ると勝手に開くから手動に切り替えたのである。八幡平の鏡沼に残雪と氷溶けが綾なす「ドラゴンアイ」を撮影に出かけた人も霧の山中で熊と遭遇し外傷を負った。
吉村昭の『羆嵐』は大正4(1915)年に北海道の開拓集落三毛(さんけ)別(べつ)で発生した事件を描いている。冬眠の時機を逸した巨大ヒグマが6人の住民と胎児1人を次々牙にかけた。人の味をしめたヒグマがガリガリ肉ごと人骨をかじる描写は凄まじい。ポリスは人間が大勢ならヒグマは逃げると考え住民を動員する。だがヒグマはひるむどころか大量の餌が来たと思っていると人々は気づく。最後は変わり者の漁師が至近距離から銃で仕留めたが犠牲はあまりにも大きかった。
秋田県角館に住む佐藤隆(りゅう)さんは和賀山塊のベテラン案内人だ。作家の塩野米松氏、今年1月に死去した写真家の千葉克介氏と3人共著で『千年ブナの記憶』(1995年)を出している。そんな彼が熊にやられ、当時の模様を新聞で語った。「私の後ろにいた客が私のすぐ横に熊を見つけ大声をあげた直後、体長270㎝、383㎏の巨体も私に気付き襲ってきた。手術用メスのような鋭い爪で右まぶたが2つに切られ、鼻も斜めに裂け軟骨は折れ、爪は歯茎の奥に達していた」「奥山の熊は先に人に気付いて逃げる。だが里山の熊は車の音や人の声に慣れていて逃げない」「発見したら人間がここにいると気付かせたり驚かしたりしてはダメだ」
食物連鎖の頂点に立つ熊は知能もプライドも高い。人間に傷つけられると執念深く復讐しようとする。だから手負いの熊は命懸けで仕留めろといわれてきた。そこで連想するのが人間のストーカーだ。事件発生前ストーカーは既にポリスから接近禁止命令を受け支配欲もプライドも傷つき怒り心頭である。妄想もストーカーの思考も変えることは絶望的で、いわば手負いの獣だ。しかも熊のように罠を仕掛け仕留めることもできない。もし運悪くストーカーや妄想の対象にされたら「三十六計逃げるに如かず」である。
13歳少女の詩『なぜ逃げてはいけないの』が昨年話題になった。なぜ逃げてはいけないの。逃げて怒られるのは人間くらい。他の生き物たちは本能的に逃げないと生きていけないのに…。角館の佐藤隆さんは山の神様に今日の安全を祈願してこう祈るそうだ。アブラウンケンソワカ…。〈2025.6.26〉

千葉克介・角館西宮家屋外展(2002年6月)



『五月雨の石ケ戸の瀬』 千葉克介