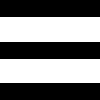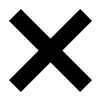6月上旬のある日曜日、「この辺で…」。写真家の千葉克介氏が車椅子から身を乗り出してつぶやくと、E夫人はバックから小箱を取り出した。蓋を開けると蚕の繭に似た形の、淡いピンクや水色に彩色された紙粘土の美しい「雲」が30個ほどぎっしり。和紙なので水を吸うとすぐ溶ける。中に入っているのは亡き夫の遺灰だ。神戸、栃木、秋田から集まった縁の深い人々は各々数個を手のひらに乗せ、1個ずつブナの森に放ち、手を合わせた。
2年前に亡くなったE先生は建築家、芸術家として著名な方で、よく働いた。3年間のがん闘病中はむろん、自宅で迎えた最期までベッド上で図面とにらめっこしていた。私のクリニックも彼の作品だが、息子さんが中心となって1周忌に企画された遺作展で、その仕事の質と量に改めて圧倒されたものだった。
作家の加賀乙彦氏は著書「科学と宗教と死」で荘子の言葉を紹介している。人間は生きている間は働く、年をとるとだんだん働けなくなる、もう働かなくてもいいようにするために老いがあり、休ませるために死がある、天が人をそういうふうに作っている…。E先生にふさわしい言葉だ。
ブナの森に撒かれた「雲」は、雨が降ると溶けて森から川へ、川から海へと下り、霧や雪となってまた山へ還る…大自然のサイクル、輪廻ですと夫人に語りかけた千葉氏は、仕事のモチーフを水と輪廻と定めて写真を撮影してきた。作品は臨死体験者が話す「お花畑」を連想させるという人が多い。彼自身も3年前に脳出血と肺炎の合併で死の淵をさまよった。そのとき向こうに三途の川がみえたという。どんな光景でしたかと尋ねたら答えた。「おれの写真にそっくりだった」
余談だが、特に法規制のない散骨はマナーが大切とされる。遺骨は自然に消え入るよう粉末化し、場所が海でも山でも、平服で、目立たぬように、むろん花束など供物はダメ、痕跡を残さず…。ところでこの「雲」、特許を取ってひと儲けしません? 夫人「夫もきっと同じこというわ。でもね…」

「雲」

散骨

大自然に還る