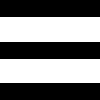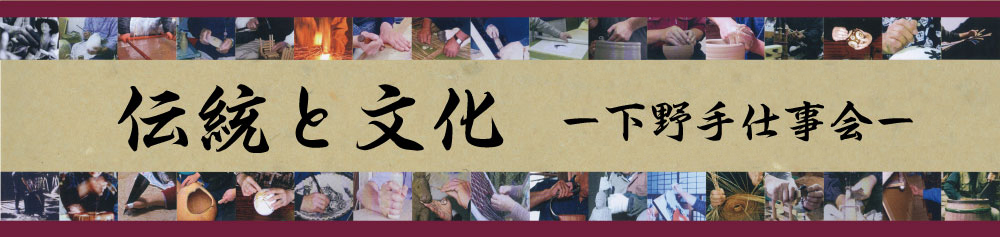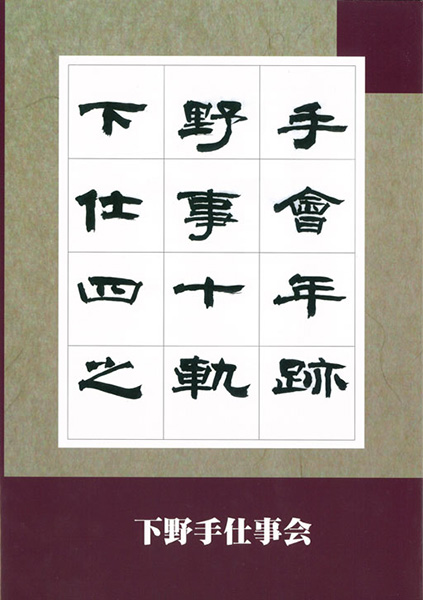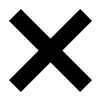伝統の技と心を後生に伝えていきたい
元禄年間より江戸紺屋の商号で染物業を創業・赤穂浪士の討ち入り装束を当家で染めたと伝えられています。紺屋時代より副業として武者絵ののぼりを制作していましたが、明治22年より本格的に武者絵のぼりを本業としました。
武者絵のぼりの起源と由来は江戸時代中期より武家社会では端午の節句には旗差物や吹流、武具などと共に鐘値の絵や武者の姿を描いて庭先に立て、立身出世と武家の繁栄を願いました。その武家社会の風習が庶民に広まり、それ以来男子誕生の祝の景物として健やかな成長を願い端午の節句に飾るようになりました。
私は門前の小僧のように幼少の頃より父、力三(栃木県無形文化財技術保持者)の武者絵を描く姿を見ながら育ち、何の抵抗もなく武者絵の道に入りました。
武者絵は手描きと型染めがありますが、手描きの技法を学び今日に至ります。武者絵のぼりは近年少子化、住宅事情により減少傾向にありますが、室内飾り、タペストリー的なものは年々増加しています。陶器にも絵付けをしていますがなかなか好評です。
今後は、現代の暮らしに合った感覚のものをおりこみながら、武者絵の良さを生かし伝統の技と心を後世に伝えていきたいと思います。





(文:大畑 耕雲/下野手仕事会40周年記念誌『下野手仕事会四十年之軌跡』P34-35より)