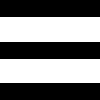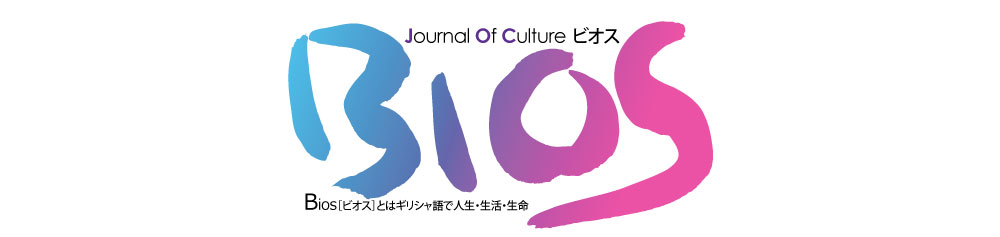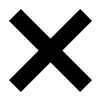450年の伝統を誇る那須烏山市の「山あげ祭り」。その舞台で講談が語られていた。語っているのは少女のようなあどけない笑顔をした「神田織乃(かんだおりの)」。張りのあるよく通る声で聴衆をひきつけていた。
「講談に出会って、まだ4年目ですから『二ツ目』を目指して修行中です」と、大きな目を輝かせて話す。栃木県那須烏山市で老舗の割烹料理店を営んでいる両親の元で、周囲にかわいがられながらのびのびと育った。
「私はこどもの頃から歌舞伎などのお芝居を母に連れられて観ていました。華やかな舞台へのあこがれがこの頃からありましたね。ダンスを習っていましたので、表現する楽しさも知りました」

講談師 神田織乃

那須烏山市「山あげ祭」で講談を上演する
歯を食いしばってやった日々
「ある日『劇団四季』を見てミュージカルをやりたいと思いました。専門学校に通いながら、いつかヒロインを演じることを心に描いていました」
家族の理解と周囲の環境に恵まれていた織乃さんは、やがて女優への道を志すようになった。「専門学校の頃からお芝居をやりたいと思って『俳優座』を受けたら、たまたま受かってしまったんですね。夢を描いて東京に行きました」
厳しい研修生としての劇団の生活が始まった。描いていた夢と現実のギャップに悩む日々が続いた。
「東京にきたら役者志望はごまんといるんですね。腐るほどいるというか……。その中で役をもらえるようにみんな必死で頑張ります。しかし、私のハスキーな声がヒロイン向きではないことや、身長の小さいことなどで、こども役か老け役、後はその他大勢の役に限られてしまいました」。頑張っても頑張っても夢に描いたヒロインは遠かった。
「歯を食いしばってやっていたんですが、オーディションも落ちまくりました。打ちのめされて打ちのめされて……。この声が好きじゃなくなってしまった。悶々としていた日々が過ぎて挫折しましたね」

取材中の織乃さん
講談師「神田香織」師匠との出会い
演劇界を志してから約7年、ある日決定的な出会いがあった。2007年度文化庁主催芸術祭参加作品「チェルノブイリの祈り」や「はだしのゲン」などの立体講談や、「ビリーホリディ物語」のジャズ講談などで評を博している講談師「神田香織(かおり)」師匠との出会いであった。
「姉が先に師匠と出会ったんです。鳴かず飛ばずで外にも出たくなかった私を心配した姉が、講談の教室に連れて行ってくれました」
師匠の講談を聞いて心を動かされた。立体講談は音響や照明を使って一人芝居のように語る。「講談協会」の中でも異色だが、女優を志していた彼女の琴線に触れた。思い切って俳優の道から方向を転換させた。師匠の門をたたき教室に通いはじめた。次第に講談に魅せられていった。
講談は江戸時代には「辻講釈師」として、軍記物に注釈を加えつつ調子を付けてわかりやすく民衆に伝えていた。また、民衆の怒りや悲しみを講談にして訴え広めていったという。後に「講談本」などの発刊に至る民衆の情報源でもあった。
「師匠のパワーはすごいです。伝えたいことがあるんです」

神田香織師匠(左)と弟子二人(右が織乃さん)
日本人として生まれた誇りをもって
日本の伝統文化は、こどもの頃から見慣れた「山あげ祭」の常磐津や母の日舞や歌舞伎見物などで、自然になじんでいて抵抗はなかった。着物で壇上に立つのも扇子にも、その慣れた環境が講談師を目指す条件は満たしていたようだ。そして、あのハスキーな良く通る声も。
2013年1月「神田織乃」の芸名をいただき正式に門下生となり2013年2月に福島県で初高座を踏んだ。
「講談の不思議な節回しを覚えるのが大変でした。しかし、張扇と扇子でリズミカルに語るのは楽しいですね。これからは講談で自分の思いを表現していきたいと思います。講談はまさに一人芝居のようで一人でいろんな役ができます。オリジナルに挑戦できるのも魅力があります」
日本の伝統文化の歴史を踏まえつつ同時に未来を臨む若い世代の講談師「神田織乃」は新たな芸で世界を目指して羽ばたく夢を語った。
「話芸を使って世界を飛び回りたいと思っています。日本の伝統文化と日本の素晴らしさを伝えたい。日本人として生まれた誇りをもって伝えたいと思っています」