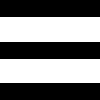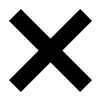企業戦士から作家へ
作家下村徹氏は1953年から1999年までアメリカと日本を往来しながら、当時盛んに用いられた言葉である「企業戦士」として企業の第一線で活躍してきた。退職後の2003年に、アメリカ滞在中の商社マンとしての闘いと苦悩の足跡を描いた小説『摩天楼の谷間から』(新生出版/¥1800+税)を書き上げた。
「小説を書こうと思ったきっかけは、当時アメリカでこんな経験をした人は少ないのではないかという気持ちがありましたから、これから商社の人がアメリカで仕事をしていく上で、いくらかでも参考になるのではないかと思ったのです」と話すかつての企業戦士は穏やかな笑顔で声楽家の奥さまと取材陣を迎えてくれた。
今や作家生活を楽しんでいるような下村氏の父親は『次郎物語』を代表作とする日本の文豪「下村湖人」である。作家の父親の後ろ姿を見て育った下村氏が、なぜ日米間往来する企業戦士としてアメリカで生きてきたのかその経緯を伺った。
「私の勤務していた会社は、戦後、日銀、横浜銀行、三菱、三井などの大手企業の後に日本の企業で9番目にアメリカに進出した商社です。第2次世界大戦前ですが、私の兄はある電気会社に就職していました。しかし戦争で全社員がクビになって仕事がなくなってしまったのです。その頃、私の父が可愛がっていたお弟子さんのなかに、当時アメリカ領地の沖縄で政財界の上層部の方がいて日本の代表になっていた。その方が沖縄と日本の間の小さな貿易会社を設立したので、兄が就職させてもらったのです。そこで一緒に働いていた日系二世だがアメリカ国籍を戦時中失った方が『アメリカと貿易したらこれからは伸びるから2人で独立しようじゃないか』と持ち掛けて兄と2人で会社を設立したのです」
その頃、下村湖人の『次郎物語』は発刊されるとベストセラーとなり、映画やテレビドラマも制作された。まさに国民的教育小説として日本全国で売れていた。
「兄は父に泣きついて資本金すべてを出してもらって始めた会社なのですが、2人のコンビが良かったのでしょうね、私の兄は人当たりがよくて営業に適した人ですし、もう一人は英語がペラペラですから、とにかくアメリカに早く出ようということになったのです」
慶應義塾大学を卒業した下村氏は英語が得意だったこともあって兄の会社に入社してすぐにアメリカに赴任した。
「コンベヤシステムとか自動車やバイクのチェーンなどの商品をアメリカで売りました。その頃の日本は、ちょうど今のベトナムと同じような状況でした。商品は船で送って私は飛行機で飛んで、売れたらそのままいていい、売れなかったら帰って来いと、今の中国、ベトナム製品のようにアメリカからすると安かったものですから売れましてね。ですからアメリカにいることになったのです。その時のことを本に書いたのが『摩天楼の谷間から』です。自分では小説を書くことになるなんて思いもよらなかった。恐らく私が物心ついたときから作家生活をしていた父の影響があったんでしょうね」

取材中の下村徹氏
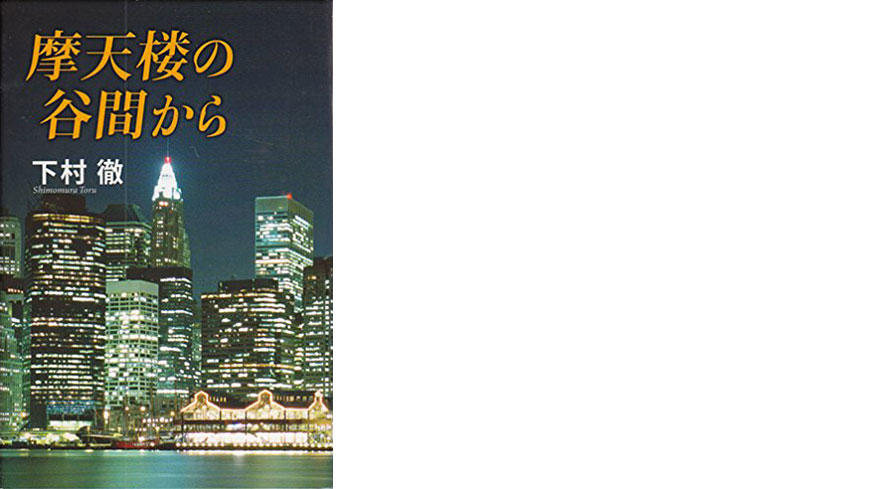
『摩天楼の谷間から』

米国、ニュージャ―ジーにある会社の前で

米国ワシントン,モニュメントの前で

米国モニュメント公園で

米国サンフランシスコで
ハンガリーの彫刻家の伝記小説に挑戦
作家下村徹氏の第2弾の作品は、ハンガリーの彫刻家で日本に帰化したワグナー・ナンドールの伝記小説『ドナウの叫び -ワグナー・ナンドール物語-』(2008年/幻冬舎出版)である。この本を手がけたきっかけは、声楽家の奥さまとワグナー・ナンドール氏の奥さまである和久名ちよさんが同じく栃木刑務所の篤志面接委員を務めていたことだった。奥さまは合唱の指導を、和久名さんは英語を教えていた。和久名さんは亡き夫ワグナー氏の足跡を記したいと思っていたが、自分ではあまりの悲しみにペンが進まないという。他の作家に依頼したのだが、なかなか書き上げることができなかった。そこで当時の刑務所長の木原洋子さんを通して下村氏にワグナー氏の伝記執筆が依頼されたのであった。
「所長さんは私の本は読んでいないと思います。恐らく下村湖人の息子だからということで口がかかったんじゃないかと思いますね。ハンガリーのことなんて全く知りませんし彫刻のことも何も知りませんでした。私の友人がブックセンターの社長をしていたので『ハンガリーに関する本を全部送ってくれ』と言ったら、彼が選んで13冊送ってくれたんですよ。読んでみたら面白かった。それで興味が出て、たまたま和久名さん主催で岩手県の学校の教頭先生たち20人くらいがハンガリーに行くので一緒にどうかと誘われて行きました。あちこち案内されて、特に本の中に出てくるワグナー作『ハンガリアン・コープス像』が素晴らしかったですね。同じ像が『ワグナー・ナンドール アートギャラリー』(栃木県益子町)にありますが室内での感じとハンガリーの青空の下で見るのとはまた違いますから」
当時、執筆のために毎週のように和久名さんの所に行って細部にわたって話を聞きだすことができたという。
「あの方の記憶力は凄いですね。あんまりいろいろと話すものですから『本当かな?』と思ってしばらくしてから聞き返すとやはり同じ。ハンガリーの内戦はさまざまな資料からですが、書くのに4年かかった。2度ハンガリーに行って調べました。幻冬舎から出版したのは『孤高のメス』を書いた大鐘稔彦先生を存じあげており、幻冬舎をすすめられたからです」
本の出版に伴い、益子町のワグナー・ナンドール記念館への来場者が増えたのは嬉しいことだと話す。何よりもハンガリーから日本に帰化した彫刻家ワグナー氏の作品を多くの人に見てもらうために。

取材中に奥さまの洋子さんと

『ドナウの叫び -ワグナー・ナンドール物語-』

ハンガリー、グループ旅行

ハンガリー、ワグナー夫人と

ハンガリー、『ハンガリアン・コープス』の前でワグナー夫人と
ラグビーに生きた青春が今もなお
約10年前に下村氏の友人のひとりが、お互いに学生時代にラグビーをやっていたことを知って「下村さん、サッカーはあんなに盛んなのにラグビーはいまひとつだ。ラグビーの解説書はたくさん出版されているが、ラグビーというスポーツがいかに作られて、どういうルールで、どこが面白いのかという本を書いてくれないか」とすすめてきた。
一度は断ったが「確かにラグビーを知らない人が多いし、書いてみようかと昔のラグビーの仲間に話すとぜひ書け書けっていうので」と、次の作品はラグビーをテーマに執筆中である。執筆は午前中、午後はゴルフの練習したりなどして、心身ともに鍛えている様子。
「ラグビーのモットーは『One for All, All for One』15人のために一人が犠牲になると皆さん思っておられるが、そうではない。Allの意味は、試合に出られない選手(クラブには60名くらいの選手がいた)やマネージャーも含めたチーム全体と思っています」
学生時代にすべてをかけたと思われるラグビーの話になると生き生きと顔が輝いて、次々に話をしてくれた。
「戦後間もない頃に慶応義塾大学に入学しましたが、ラグビーは『クラブチーム』が本来の姿なのです。私が属していたのはKEIO J.S.K.S. CLUBという日本最古のグラブチームです。今は、学校代表とか企業代表のチームが注目されがちですが、本来はクラブ中心のスポーツです。大学時代は毎週試合に出ていました。その頃には前歯を失いましたが、体は小さくても足が速かったものですからポジションはスクラムハーフでした」
ラグビーは慶応義塾大学のエドワード・ブラムウェル・クラーク教授が初めて日本に紹介。その5~6年後にラグビー協会ができたという。
「それから2年後にJ.S.K.S.ができ、一年後に早稲田にもG.W.というクラブチームができた。慶応のラグビー部は学校がスポンサーになって学校を代表するチーム。ラグビー発祥のイギリスの本場の精神にのっとって同好会で好きな者が集まってやれというのがクラブチームです。ラグビーは試合が終わったらノーサイドと言う。試合終了とは言わない。ノーサイドの精神で闘いが終われば敵も味方もなくなって肩抱き合うのがいい。All for Oneとノーサイドの精神が、今執筆中の小説の核になるのかな」
ラグビーの小説はまだ筆半ば、完成を待つ仲間たちの声援のなかでゴールを目指している。「私の一生はラグビーをしてなかったら全く変わっていたでしょう」

試合後の集合写真(学生時代)
父「下村湖人」の思い出
「父との思い出はいろいろあります。戦時中父は地方のお弟子さんの所に疎開することをすすめられましたが、疎開するのは嫌だと言って東京にずっといたのです。母は体の弱い人でした。食料はないし空襲で家も焼けて、だいぶ辛い思いをして倒れてしまったのです。終戦の年の9月に某大学病院に担ぎ込みましたが、若いお医者さんが輸血をしたら血液型が間違っていて49歳で亡くなりました。だから父はそれからずっと一人でいましたね。終戦の年に『次郎物語』が売れ始めて、終戦後は爆発的に売れましたから、経済的にはとても豊かになりましたが……」
下村湖人は台湾の高等学校(現在の台北大学)の校長として赴任していた当時、学生たちがストライキを起こしたことがある。政府が「全員退学処分」と決定したのを湖人は「現地の優秀な将来有望な若者を退学させたら台湾は一体どうなるんだ」と反対、校長辞職と引き換えに全員学校に戻したというエピソードがある。そのために教師の資格を失い帰国。下村氏がまだ1歳のときであった。東京に戻り、学生時代から信奉している田澤義鋪氏(第五高等学校の先輩/政治家)の世話で小金井市にある青年教育道場の所長に着任した。
「終戦まではその給料だけでしたから生活は苦しかった。戦後は『次郎物語』が売れましたから経済的には良かったのですが、兄の会社にだいぶ投資して、そこそこ会社が上手く行きそうだった頃に亡くなりました。父は『愛情というのは植物に対する肥料と同じであんまり近いと焼けてしまいます。遠いと届きません。愛情というのは近すぎてもいけないし遠すぎてもいけないと思います』と言っていましたが、作家、教育者の父としての言葉で一番初めに浮かぶのがその言葉です」
父親の執筆している背中を見て育った下村氏が、今父と同じ道を歩んでいる。若くして亡くなった母と父を懐かしむようにさまざまな想いを話してくれた。
「父はカリエスで手首の骨が溶けても書いていましたよ。寡黙で、私たち子どもにとっては怖い父親だった。亡くなる5日前まで当時珍しいウイスキーを飲んでいました。私は6人兄弟の一番下ということで可愛がられた。一番上の姉が母親代わりに面倒をみてくれました」
取材陣にお茶をいれてくれた下村氏の奥さまの洋子さんは、東京藝術大学を卒業後ドイツに留学し、帰国後は声楽家として活躍。また合唱団や幼稚園での音楽指導などの他、個人レッスンなどで後進の指導にあたっている。下村氏のラグビーの大先輩ご夫妻が、アメリカで企業戦士として闘っていた下村氏を紹介、仲人になり洋子さんと結婚したという。
「下村湖人の息子だと知って驚きました。『次郎物語』は中学生のとき一生懸命読んでいましたから」と洋子さん。次に発刊される予定のラグビーの小説が完成するのを、多くの関係者とともに密かに心待ちしているかと思うが、愛妻の声援が元ラガーマンを最も奮起させるに違いない。

家族の写真―台湾時代、父、母、長男は死亡、
姉、兄、姉、姉、下村氏

家族で千葉で海水浴

戦後の家族

声楽家の奥さまと自宅にて
(取材:アートセンターサカモト・ビオス編集室/2017年11月29日)