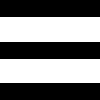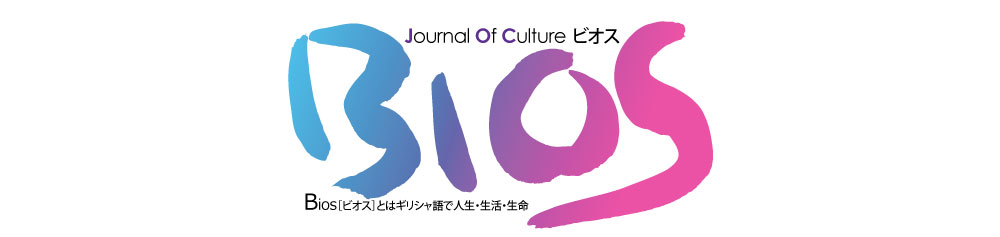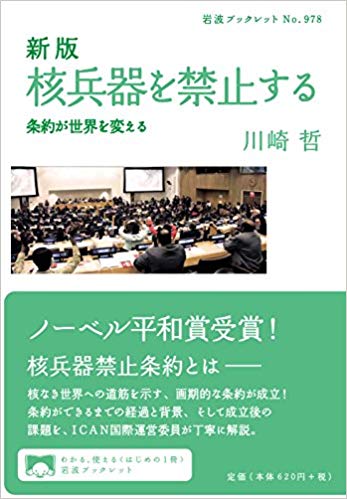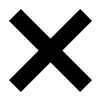2017年10月、ノーベル平和賞のニュースに世界中が沸いた。国連における核兵器禁止条約の成立に貢献してきたNGOの連合体であるICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)にノーベル平和賞が授与された。「核兵器の使用がもたらす破滅的な人道上の結末への注目を集め、核兵器を条約によって禁止するための革新的な努力をしてきたこと」(ノーベル平和賞授与式委員長演説/17.12.10)という理由であった。
ICAN国際運営委員でありピースボート共同代表の川崎哲さんにお会いすると、受賞の喜びと平和運動への思いを込めた話を伺うことができた。

国連での発言

授賞式出席(左から3番目)
(写真提供:ICAN)
ノーベル平和賞はICANの活動を最大に認めてくれた
「ノーベル平和賞の受賞は驚きました。大変光栄なことです。感激しました。ICANは『核兵器禁止条約』を作るという目標を約10年前に掲げて邁進してきました。『核兵器禁止条約』ができてもすぐに核兵器がなくなるわけではありません。しかし『核兵器禁止条約』ができなければ核はなくならないのです。その入口の扉が開いたのです」
川崎さんは平和活動を「一里塚」のようと例えた。一里登って見上げると頂上はまだまだ高くて遠い。「しかし一里登れた、自分たちの足で歩いてきたという実感がある」と話す。「現実的な目標を見つけて達成させることは、活動を継続する上で大事なことです」
達成したという実感を持つようなプラン作り、仲間作りをして、声を掛け合って前に進んでいることを確認し合いながらやってきたという。「それがよかったと思っています。そういう意味ではノーベル平和賞は『ICANの活動は重大な意味がある』と、これ以上ない形で最大に認めてくれた。大変嬉しいことです」
ノーベル平和賞で評価を得た川崎さんらは、次の課題としてまず第1に多くの人々に核の問題を知ってもらい日本の核政策が変わることを目指している。もう1つは自分たちのやってきた活動を受け継いでいく人たちを増やすことであるという。
「しかも日本で増えることが大事なこと。私の足は日本の地についていますから。世界で活動していると、結局取りえは日本語が話せることです。日本語が話せるということは日本の人に一番よく伝えることができる。これほどの特技はない。ですから日本を故郷として日本で生活している人に頑張ってもらいたい。活動をさらにより良い形で広げていけるような次の世代をつくっていくことが大きな課題の1つです。私はピースボートの若いスタッフやたくさんのボランテイアの人たちがこれらの活動を受け継いでいくような仕組みを作っています」

取材中の川崎さん、ピースボート事務所にて(2018年6月6日)
お世話になった国の人たちのために
川崎さんは大学時代にバックパッカーでいろいろな国を旅している。1988年に一度中東地域を訪れたことがあった。イラン・イラク戦争が終わった直後のイランである。戦争があった地域だから「どんな感じかな?」と野次馬根性で入国したという。
「どうせ知らない国で言葉も通じないんだったら、むしろそういった国に行ってみようと思った。行ってみたらイランの人に大変優しくしてもらったんですね。家に泊めてもらったり、家族や親戚まで紹介してもらったり。一介の日本人学生の旅行者にもかかわらず温かなもてなしを受けたのが忘れられません。中東では危険な目に合った旅行者もいましたので、たまたま素晴らしい人たちに出会えてラッキーだったと思います。以来その地域に深く関心を持つようになりました。その人たちがさらに戦禍に見まわれる、大変なことになると思いました」
1990年にイラクが隣国のクウェートに侵攻、91年にアメリカが加担して「湾岸戦争」が勃発した。それからの川崎さんは平和運動へとのめり込んでいった。
「大学生だったので、湾岸戦争に関しても同世代でいろいろディスカッションできればと思っていました。しかし当時の日本の若者たちはあまりにもは政治に無関心でした。今のほうがまだいいくらいですよ」
それでも川崎さんら首都圏の学生がグループになって、「戦争反対」「日本政府による戦争への協力に反対」するアクションを起こし始めた。
また、当時イラン人の男性労働者が大勢来日していて建設労働などを主な仕事としていた。川崎さんはイランの人たちにお世話になったという思いがいつも胸の内にあり、外国人労働者の支援活動に取り組んだ。
「外国人労働者への賃金未払いや労災に関することなどたくさん問題があって、若いメンバーで少しでも手助けできればと動いていました。お世話になった国の人たちのためにと一生懸命やっていると、日本の社会の構造的な問題が浮かびあがってくるんですね。やはり政府は冷たいとか法制度に穴があるとか、活動そのものを通じていろいろなこと学びました」
同じ志を持ったメンバーたちと会を作り大学卒業後も運営を続けていた。さまざまな支援活動を広げていくなかでNGOの運営も身に付いてきた。
「企業じゃありませんから、会員を募って会費を集めて何とか回していく。そういったことも学びました。ベトナム戦争の頃から反戦活動を地道にやってきた先輩たちとも知り合い、やがて平和問題の中でも専門的に核兵器の問題を取り上げて国際会議に参加する機会も得ました。そうした流れで今の活動に繋がっています」
父から子へ
川崎さんは世界を廻るピースボートの活動から帰宅すると、一人息子に他国の情勢を話して聞かせていた。いつも分からなくても黙って聞いていた息子が、小学校2年生の時に起きた原発事故(2011年)後、はじめて川崎さんに質問してきたという。
「原発ってどうなの?と聞いてきたんですね。突然そんなこと聞かれたので『あれっ』と思った。福島の子どもたちがみんなマスクをつけていたのをテレビで見ていましたから、それで私に聞いてきたんだと思います。自分たち子どもが被害者になるというのを直感したのだと思います。『シリアで戦争になっているから考えろ』と言ったところでなかなか無理なことですが、自分と同じ子どもたちがマスクをつけているとなったとき、これから将来どうなるんだろうかと、子どもは真剣に考えるんです。今の日本は、子どもたちの将来はどうなるのだろうかと真剣に考えて、社会が行くべきビジョンのようなものを議論する風潮がなくなってきているのではないでしょうか」
川崎さんが中学2年生のときに父親(川崎昭一郎/千葉大名誉教授・元財団法人第五福竜丸平和協会会長)が広島に連れて行ってくれたという。1982年当時は世界的に反核運動が盛り上がっていた。ニューヨークで100万人が「核兵器反対」でデモをしていたという時代である。
「父は物理の先生で、『原水爆禁止』に関心がありました。あの頃、子ども心に核戦争が現実の脅威だって認識がありました。中学生のときに『世界の問題にどんなことがあるか』と聞かれて、『アメリカとソ連の核戦争』と答えた覚えがありますが、特別なことではなくて、みんなが感じていたことの一つだと思います」。テレビをつけると「米ソの核の脅威」などが放映されていたような時代であった。
「大学に入って途中から平和活動のきっかけができて動き始めたのですが、父の影響はあったと思います。私は家庭では好き勝手に活動していて妻にはあきれられていますが、昨年中学3年生になった息子を初めて広島連れて行きました。よく分からないという顔をしていましたが、私も父に連れて行ってもらった頃はよく分かりませんでした。しかし心に留めていましたから、今は分からなくてもやがて平和への思いはつながっていくと思っています」
明確な目標に向かって前進する
川崎さんは「ピースボート」で世界を巡り、様々な国で子どもたちと出会うが、大都市でホームレスの子どもたちをたくさん目にするという。
「日本は貧困問題が深刻になってきているとはいえ、子どもが町中で寝ているという状況はまだ見られない。船で巡る半分以上の国でそのような子どもたちに出会います。その子どもたちの姿を見ていつも胸が痛みます。大変な社会の中でも子どもたちが必死に生きている。『今日、明日、自分たちはどうやって生きていこうか、どうやって自分たちの国を発展させていこうか』と、真剣に考えている若者たちがいる。残念なことに日本では将来どうあるべきかなどの議論が欠落していると思えてならないのです」
日本の大人たちはあと10年20年生きるだけの蓄えがあるから、とりあえず何とかしのいでいって、ありとあらゆる政治的な問題や経済的な問題、危険なことや難しいことは次世代につけを回すようなやり方をしていると指摘する。
「2011年の原発事故はその1つのいい例です。事故が起きたときは『想定外』と言っていたが、『実は想定できていた』という話がどんどん出てきた」。とりあえず起こり得るかもしれないが、起きないだろうなどと思い込む。何とかやりくりしていて結局大失敗してしまう。いわゆる「つけが回ってきた」と。
「しかし私たちがやっていることは砂漠に水をかけているようなものです。平和運動は大変な時間と労力をかけても一向に先が見えないような活動です。ICANがノーベル平和賞をとったからといって明日核兵器がなくなるわけではない。『一歩』を評価されただけですから。平和活動をしても実は何の意味もないのではないかと思われることもあります」
今の世界および日本の政治的、経済的状況の中で、核のない世界を目指しても核のない世界はあまりにも遠い。世界平和などはとてつもなくもっと遠い。しかし、それでも平和活動を続けてこられたのは、「NGO活動を通して世界中に仲間ができたことが大きかった」と川崎さんは話す。
「世界中にいるNGOの仲間たちはすごく現実的で賢い。世界中でNGO活動をがんばっている人々に出会って知ったのは、大変な状況のなかでも極めて明確な目標をきちんと設定して、その目標に向かって一歩一歩前進しているという事実です」
昨年10月のノーベル平和賞受賞以来、川崎さんに各地域の大学や団体からの講演依頼がたくさん寄せられている。
「ノーベル平和賞を受賞したことによって、今まで核兵器禁止などを考えてこなかった人たち、またそのような話を聞く機会がなかった人たちが講演にきてくださいます。世界的な大きな賞を受賞したことの手応えを感じますが、そのような人たちに話を聞いてもらえる場を、さらにより多く持ちたいと願っています」

ベアトリス・フィン事務局長(右)と

サーロー節子さんと
(写真提供:ICAN)