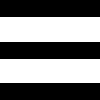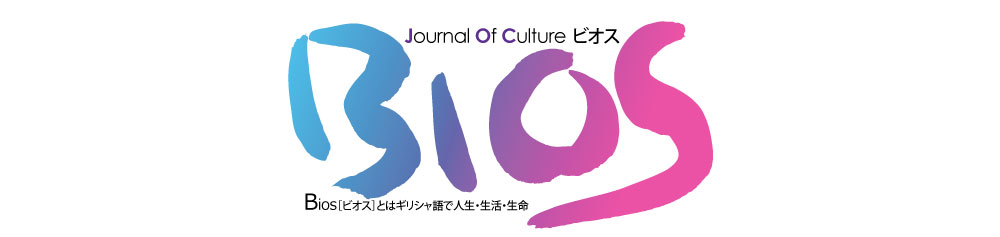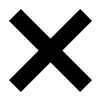今の時代を創るのは自分たちです
「土はこちらが何もしなければ動かない。どうしたいかはあくまでも自分の意志。120パーセント土は受身です。逆に土が『どうしてくれるの?』と、問いかけてくるのです」
陶芸家、林 香君はあふれる思いを抑えながら「土」を語る。久しぶりの対面だったが、トレードマークのみごとなロングヘアが短く切られていた。取材当時はハイデルベルグで展覧会(7月30日まで)の最中でもあった。トルコに学生(文星芸術大学)を率いてのワークショップから帰国した翌月、栃木県宇都宮市の城山西小学校でこどもたちに陶芸を教えていた。小規模特認校として「新たな学校の創造」をテーマに、芸術、文化の分野で活躍しているアーティストを招いて、「こどもたちの豊な感性を育む」ために特色ある教育を推進している小学校である。取材は校長先生の許可のもとに小学校で行われた。
ロクロ修行
「体験ではなくて、修行です。1、2時間のロクロの体験教室はどこでもあります。昨年は日数を短くして、たくさんのこどもたちに体験させましたが、1、2時間だとこちらも『まあいいか』ってなります。今年は5日間通して来られるこどもたちが参加しました」
一点に集中して、真剣なまなざしでロクロを回すこどもたち。1年生から6年生まで小グループに分けて、ロクロを囲み作品を作る。
「粘土という土の持つ魅力、そこにいろんな示唆があります。大地には豊かで多様な表情があります。たとえば田んぼ一つとっても、日照りが続けば表面が乾き、土の質によっても、乾燥の速さでも、ひびの入り方が違う。実に多様な表情を見せてくれる。そういうちょっとした身の回りにある地球の環境全般を観察していく力を育てたいと思います。それは何も陶芸だからではなくて、自然全体を感性豊かに受け止め、観察し分析していく力を育てていきたいと思っています」
こどもたちの顔をのぞきこんで「どういう形にするか土に聞いてごらん?」と問いかける。
「もちろん集中してじっとしていなければモノって見えてこない。全体も部分も見なければならない。見る方向によってもとらえるものが違うことを、土を通して気づく、気づかせる。これはあくまでもこどもたちと私の間に土があるからこそコミュニケーションが成り立つ。土という共通言語を見つけながらこどもたちは先生の何気ないことばも敏感に感じ取っています。技術道具の使い方を教えますが、テクニックを教えるのではない、それを知ってどう使うかは自分で決めることです。5日間、こどもと土と対話しながら……。それで『ロクロ修行』とつけました」



アーティストとして、教員として
ハイデルベルグでチェコ人作家と「海の音シリーズ」の展覧会。パリのセーブル美術館での陶芸展。アメリカでの巡回展(ニューヨークの美術館が作品を買い上げる)。パラミタミュージアム〈三重県)で出展した華厳シリーズがロサンゼルスのラクマ美術館で展示が決定しているなど、この2、3年を見ても、アーティスト林 香君は世界の芸術界に日本の陶芸家として名を馳せている。同時に大学の教授として、若いアーティストを育て世に出すという大きな責任を担っている。
「約4年半前に、恩師三浦小平二先生(人間国宝・東京藝術大学名誉教授)が亡くなられて、表舞台に自分ががんばって出なければ、学生たちに後姿を見せなきゃいけない、とにかく前に進んで学生たちを引っ張っていかなければと思いました。逆に引っ張られているのかもしれませんが」。それは「次の世代のために何をしなければならないか」という絶えざる問いかけでもあった。
「学生たちにとって今は非常に『悪い時代』といわれていますが、過去には戦争や昭和の大不況、石油ショックなど、その時代時代を私たち人類はずっと生きてきているわけですから。今がいくら悪いといっても、そんな比較はできるわけではありません。自分が今の時代に生まれたことを背負って、新しい何かを切り拓いていかなければならない、みんなで前を向くしかない。この時代に生まれたことの意味があります。乗り越えていかなければ。今の時代を創っていくのは自分たちなのです」
6月には、トルコのアナドル大学へ大学院生を連れて行き、聴覚しょうがい者のためのワークショップを実現している。
「同行した学生らが大学で学んだことがそのまま海外で通用することに気がついてくれた。それが大きな収穫でした。今までは基礎基本システムに時間をとられていましたが、発信型に変えていかなければと思います。作品は常に深化させていかなければなりませんから。そしてここ数年、作品は海外とのつながりが多くなりました」



『きらめきの形』
「焼き物は永遠性があります。一度焼いたものは戻らない。真摯に土に向かうだけです。どういうメッセージを与えてくれるのか。絶えず土に問いかけています」
震災の鎮魂であるドイツの展覧会の作品に「命の誕生」が加えられたという。「命の尊い存在のきらめきでもあります。尊い記憶の形としても……」
9月に栃木県宇都宮市で開催される個展のテーマは『きらめきの形』である。命が輝く瞬間に繋がる作品を発表する。
「自然が無言でいろんなことを伝えています。私たちは、その無言を真摯に受け止めて丁寧に読み取ることです。ゆっくりと生きながらね」
最後に長い髪をバッサリと切った理由を聞いてみたかった。かえってきた答えは、次世代の芸術を託される若い学生への、師としての魂のことばであった。
「学生はプロの陶芸家ではないかもしれない。しかし、その一歩手前まで必死でやらなければ抜け出せない。仕事に集中しなければならない。甘いやり方ではだめです。ひとつの決別の覚悟が必要です。その覚悟をこのような形で学生に見せたかったのです」