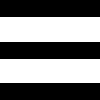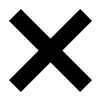黒井 治(くろい おさむ)は、私にとって不思議な存在であった。彼は私の展覧会のオープニングパーティに、いつも雲の上を歩いているような軽い足取りでニコニコしながら現れた。抜群のスタイルでお洒落で男前、いつも冗談を言いながら楽しそうにワインを飲んでいた。後に彼がダンサーと知ったときに、軽やかな足取りもしなやかな動きも絶やさぬ笑顔もそのすべてが納得できた。今回のインタビューでさらに彼の幅広い芸術の世界を知ることになった。

舞台芸術家-黒井治(photo-Douglas Lyon)

パリのカフェで黒井治とトモコ・オベール
一流の指導者に出会って
黒井の父は三菱重工業神戸造船所の造船設計技師、母はピアニストであった。当時としては裕福な家庭で何不自由なく、好き放題甘やかされて育ったという。
「母の思いもあって小さい頃からピアノを習っていました。親がすべてをやってくれたので、このままではいつまでも親に頼ってしまうと思い、親の手から離れたかったのです。非常にませていたんですね。東京の演劇系大学も考えましたが、経済的にも自立したかったので特待生システムのある大阪芸術大学を選びました。学年トップ一人だけの特待生枠で通し、四年間学費はゼロですみました。生活費はモデルや映画のエキストラ、そして舞台出演などで随分稼ぎました。とにかく早く大人になりたかった」
早熟で独立心旺盛な18歳の出発である。大学では舞台芸術学科の演技演出を専攻、しかし必修で週2~3時間はダンスも習うことになっていたが、このことが彼の人生を思わぬ方向へと転換させることになった。
「それぞれのコースで日本の一流の指導者が教えに来ていましたが、私は特にクラッシック・バレエの法村牧緒先生(法村友井バレエ団団長)に見い出され、3ヵ月後には先生と同じ舞台に立っていたのです」
ダンサーとしての素質は大学に入ってから見い出され、その才能は素晴らしい指導者に出会って開花しつつあった。しかも学生の身分で破格の出演料をもらったという。
「バレエ公演で稼いだお金で自分の好きな芝居の公演ができました。その他に200万円位の貯金をしましたが、これが後の渡航費用になったのです」
驚くほど華々しいダンサーのスタートであり中身の濃い学生生活であった。自信に満ちた青年期を謳歌していたかに思えるが才能だけではなく弛まぬ努力も怠らなかった。「天は自ら助くる者を助く」の日本語のことわざを思い出す。
自分に妥協しない
1979年は黒井にとって人生最大のチャンスの時であった。フランスの演出家で俳優のジャン=ルイ・バロー(*1)の何度目かの来日公演があった時、「ハムレット」「繻子の靴(しゅすのくつ)」を見てその舞台に衝撃を受けた。
「楽屋に行って、英語で必死に自分の事を話したのです。彼はとても疲れている様子でしたが、私に大きな名刺をくれました。『君のことを説明した手紙を書いて送るように』と言われました。一生懸命辞書を引きながらフランス語で書いて送ったのです。フランス語なんて全く分からなかったのですが、とにかく夢中でした。返事がくるかどうかは半信半疑でしたが、何と2週間後に彼から手紙が届いたのです。『これを持ってフランスに来なさい』と書いてありました」。1981年、卒業後日本の生活を打ち切って新天地へと向かった。
「フランスは伝統のある演劇界をはじめ総合芸術の国である。古典の土壌からもう一度基本を学び、演劇の未来を検証する」と言う強い意志を持ってパリに乗り込んできた。
彼は日本ではすでにいくつもの演劇活動を展開していて壁にぶつかっていたからだ。また70年代の日本の演劇界は低迷していたのでパリ行きは良いチャンスでもあった。しかし、パリに着いてから彼の前に壁のように立ちはだかったのがフランス語であった。
「ソルボンヌ大学のフランス語講座よりもモリエール(*2)の長台詞の暗記が功を奏し、念願の国立コンセルヴァトワールの演劇科に合格し、4年間演劇三昧の毎日を送ることができました」と話す。
才能プラス努力を惜しまない彼は、何千回、何万回とフランス語をテープで聴いて、フランス人のように「美しく、正確に、早く」話す朗読術の驚異的な鍛錬をした。努力が結実して1年間でフランス語をマスターしたという。
「自分に妥協しない、徹底しました」と、23歳の若さと強靭な精神で目標を達成させた。その後、当時ロン・ポワン劇場を拠点とするバローに、後にシャイヨー国立劇場の演出家アントワーヌ・ヴィテーズ、マルセイユのマルセル・マレシャルの巨匠たちに演出を師事する。さらにマルセル・マルソー(*3)からパントマイムを学ぶ機会をも得ることができた。

バレエのレッスン指導中の黒井氏(photo-Etsuko TAKANO)

公演のリハーサルで(photo-Julie Cohen)
演出家、そしてダンサーとしてフランスで活動する
「能と狂言」の研修のために一時帰国して京都に在住していた時に、モンペリエ大学文学部演劇科のゴンタール教授(「17世紀の劇作家ジャン・バティスト・ラシーヌ」の研究者)に会った。彼は教授に東洋と西洋の演劇比較研究をするように薦められ、南フランス・モンぺリエ大学の演劇研究所でアカデミックな理論を研究している。
「大阪芸大でやはり必修で『狂言』を稽古した経験を生かし、京都大蔵流の茂山忠三郎先生に師事、狂言の明晰な話術と日本古典の踊りや動きも習得しました」と、黒井は日本の伝統芸能をベースにフランスの演劇を取り込んで独自の世界を切り開いていた。
1988年、留学期間が過ぎ帰国を考えていた時に、ベルギーのブリュッセルの劇団ポエムから電話があった。「『ユーロバリア』という文化の大イベントにおいて日本演劇の感性で現代演劇を創作して欲しい」という依頼であった。彼は依頼を受けて、ギリシア悲劇をテーマに、能の持つ普遍的な演劇性を現代に活かす演出で上演した。演劇は大きな反響を呼び、新聞紙上で賞賛されTVにも採り上げられるほど話題になった。
「すると次々とオファーがきました。それならばと帰国せずに、フランスに留まってこの地で活動していこうと決意したのです」
国立ダンスセンターのサボルタ振り付けのコンテンポラリーダンス「カルメン」では主役ドン・ホセを踊り、ダンサーとしてデビューした。「カルメン」はパリ市立劇場、リールオペラ劇場を皮切りに1年間ヨーロッパ各地を遠征公演した。
ルーマニア革命勃発(1986年)後、文化省の招きで首都ブカレストのオペラハウスでも踊ったのは「歴史的な出来事」として評価されるほどであった。

公演のリハーサルで(photo-Julie Cohen)

ギリシャ・クレタ島の海岸でのパフォーマンス(photo-Kuros)

国立ギメ美術館で披露した狂言(photo-Daniel Lifermann)
最悪の事態を我が娘に救われる
順風満帆と思われた彼の輝かしい人生の半ばに突然の病魔が……。1992年、新作バレエの稽古中に重症の椎間板ヘルニアとなり半身不随のような状態になってしまった。
「33~34歳の頃で精神も肉体も最高潮の時でした。肉体は決して20歳代のままではなかったのですね。身体はしだいに下方に、芸術性は上方に、その隙間をやられたという思いでした。しかし踊り手の職業病として少なからず皆さん経験します。早いか遅いか人によって異なりますが、バレエは自然体逆行のアラベスク(片脚でつま先立ち、他方の脚を後方へ高く上げバランスを取り静止する)などで踊りますから、背骨・骨盤に負担がかかりヘルニアを誘発するのは仕方がないことです」
この年に長女リュドミラが誕生、それを期に妻の実家である南西フランスのモンペリエに移住した。「もう舞台に立てないと覚悟していましたから」
モンペリエの大学で、演劇・ダンスを指導する傍ら『日仏文化協会』を立ち上げ日本語講座を開設しました。「自分は食べなくても子どもには食べさせなくてはと必死でした。私のそれからの人生は我が娘に救われたということです」
長女リュドミラの名は、彼の敬愛するロシア人のボリショイバレリーナとフランスの名女優から名付けたと嬉しそうに話してくれた。
「しかしダンスをやめた訳ではありません。自分の身体をコントロールできるようになり、動きを調整できるようになったのです。2011年にパリのオペラ座でモーリス・ベジャール(*4)振付の「ボレロ」の群舞で踊ることができたのです。私は50歳を過ぎていましたが、オーディションにパスしたのです。公演後ニコラ(*5)は、私の踊りを評価してくれました。やはり嬉しかったですね。実際はきつかったですよ。ご存知のように中腰でひざを曲げ少しずつ変化させていく動きなので大変でした」彼はダンサーも役者も、音楽性がないと難しいというが、「私はピアノを習っていたことが大いに役に立っています」と。
舞踏ダンサーとして高名な大野一雄(*6)のパリ公演では、フランス文化省からの依頼を受け黒井が通訳として2週間行動を共にしている。
「最初、彼の言葉は特殊で何を意味しているのか分りませんでした。それは創作コンセプト・哲学だったのです。それを通訳するのは大変でしたが、私も舞台に立っているので徐々に理解できるようになりました。当時92~93歳の彼の舞台に感動し震えました。私の通訳に満足してくださり『こんなに分かってくれた人はいない』と言ってくださったことが忘れられません」
今、彼は演出や振付の創作以外に、昨年末、国立人形劇学院・国際人形劇研究所の招聘でマスタークラスを指導している。
「指導も真剣勝負です。私はよく怒鳴るのですが、泣き出す生徒もいます。ただ一方通行ではなく、生徒から倍くらいのエネルギーが跳ね返ってきます。即興などをやらせると逆にこちらが学ぶことが多い。最終日の夜に生徒たちが観客を前にしてアトリエ公演を行いましたが、彼らの能力の可能性がどんどん広がってワクワクしました」
感性と理論、体と精神これらを高度に追求し、最高の美を追い求めている人がここにいる。頂点にいる人は将来頂点に立つであろう若者の才能を見抜き、手を差し伸べる。若者は持てる才能の限界までの努力で応答する。こうして文化・芸術が長い間継承されていく。舞台芸術家、黒井治の人生そのもののように。
オペラ座に近いパリ2区の夜のカフェで、彼との話は尽きることがない。この魅惑的なパリの街で美味しい白ワインを心ゆくまで堪能した。
1)ジャン=ルイ・バロー(1910-1994) フランスの俳優・演出家・劇団主宰者。日本では映画「天上桟敷の人びと」のバチスト役及び3回の来日公演などにより知られた。
2)モリエール(1622-1673) 17世紀フランスの俳優・劇作家。コルネイユ、ラシーヌと共に古典主義の3大劇作家の一人。劇団はフランス国王の寵愛を受け、現在のコメディ・フランセーズ劇場の前身。
3)マルセル・マルソー(1923-2007) フランスのパントマイム・アーティスト。この芸術形式における第一人者で、パントマイムで最も有名な人。「パントマイムの神様」「沈黙の詩人」と呼ばれた。
4)モーリス・ベジャール(1927-2007) フランスのバレエの振付家。東洋の思想や日本文化への関心も高く、三島由紀夫をテーマにした「M」、「仮名手本忠臣蔵」を下にした「ザ・カブキ」などを振り付けており、「春の祭典」、「ボレロ」など40近い作品を残している。スイスのローザンヌでベジャール・バレー・ローザンヌを主宰。
5)ニコラ・ル・リッシュ(1972-) 2014に引退するまでオペラ座エトワール・ダンサーとして国際的に活躍。シルヴィ・ギエムとの共演は有名、「ボレロ」のソロは得意な作品の一つ。
6)大野一雄(1906-2010) 舞踏家。103歳まで舞踏家としての姿勢を保った。

フランス銀行で行われたガラ公演で披露した狂言(photo-Daniel Lifermann)

野外での茶会(ブローニュの森の公園)
TOMOKO K. OBER(パリ在住/画家・ミレー友好協会パリ本部事務局長)