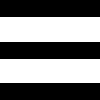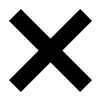パリの新潟県人の集まりで出会ったピアニスト成嶋志保さん、2014年に初めて彼女のピアノコンサートに行った。私はいつものように白紙の状態で聞いていたが、後半のリストの曲の最中に突然、涙をはらはらとこぼしてしまった。
それは約7年前、ポーランドのショパンの館の庭園で、ポーランドの女性ピアニストが弾いたショパンの曲を聴いた時に流した涙と同じであった。

ピアニスト成島志保と筆者トモコ(右)。パリの新潟県人会の原田哲男会長の自宅にて
ナントと新潟を結ぶ架け橋
パリより約380km西、ロワール河畔にある都市ナントは大西洋への玄関口である。ナントは新潟県と姉妹都市であり成嶋さんは姉妹都市設立に貢献し、以来ナントに在住している。ナントやパリを中心にコンサート活動を続けている。
「パリなどの大都市から見ると、ナントなどのフランスの地方都市の速度は50分の1くらいの遅さですが、私はニューカレドニア(オーストラリアから約1000Km東にあるフランス海外領の島)や、他のヨーロッパの町に在住して知っていますので、どの町でもどのような速度でも大丈夫です。夫の仕事がきっかけでニューカレドニアの首都ヌメアに3年間滞在しました。常夏の島で観光客も多く訪れます。ニッケルが発掘されているので、経済的に豊かな島です」
速度という言葉が出てきたのはミュージシャンゆえか!さまざまな国の文化に実際に触れて知っているミュージシャンであり、ナントと新潟を結ぶ架け橋の役目を果たしているピアニストである。1989年の第24回新潟音楽コンクール優秀賞を皮切りに各国のさまざまなコンクールに入賞している。

バリトン歌手レミー・シャルルーコフマン氏とのデュオ・リサイタル
親子3人でパリへ
「生まれは東京の国立でしたが、父が新潟大学で助教授の職を得た関係で私が2歳の時に新潟県新潟市に引越し高校まで育ちました。私にとって新潟が故郷です。4歳からピアノを習いはじめてずっと現在まで続いていますが、高校2年生の青春のまっただ中、お転婆で楽しい学生時代を送っている矢先に、父の研究留学に伴い渡仏が決まりました。ピアノで1年間パリ・エコール・ノルマル音楽院への留学資格を得ましたが、当時はフランス語が全く分からず、高校の友人達と離れるのも悲しく、どこの国であれ日本を離れる事など考えられなかったことを良く覚えています」
最初の頃のパリの生活は日本と大きく異なることの連続だったと話す。ようやく探し当てたアパートの上階に作家が住んでいたため、ピアノの音はやめてほしいと言われ、毎日貸しスタジオ通いを余儀なくされたという。
「滞在許可証が何ヶ月も取得出来ず、何度も警察に届けを出しに出向いては心細い思いをし、それに加え日常の小さなトラブルの数々!どんな些細なことにも、解決するのに日数がかかるという不便さから、『忍耐を持って待つ』ということなどは、日本を離れなかったら全く分らなかったと思います。現在私がここにおり、ピアニストとしてヨーロッパで活躍する事ができるのは、両親と周りの先生方の後押しと、家族3人でのパリでの貴重な1年間の経験がとても大きな要因だと思っています」

ポワティエのオランダ人邸宅でのコンサート

再びパリに一人で
「1年の留学期間の終了が近づいてきた頃、私はこのままパリに残りたいと両親に告げました。『せめて高校を卒業してから』と説得され、3人で日本に帰ることになりましたが、新潟では進学校に在籍していて、ピアノを優先させるには難しい状況でした」
音楽中心の生活を優先するため東京音楽大学付属高校に編入学し寮生活をした。しかしフランスと日本のピアノ教育のシステムの違いに愕然としたと話す。
「例えば、日本では年度始めに2、3曲、多くても5曲のピアノ曲を先生と一緒に選び、それを一年かけて弾き、年度末に試験で演奏します。フランスで私が最初についた先生は、30曲近くの曲を渡してくださりました。それを徐々に弾いていき確実にレパートリーを広げるのです。附属高校では幸いにもフランスを良く知っている素晴らしい先生に出会い、とても励まされました。早稲田にいたフランス人研究者と交流したり、機会を見つけてはフランス語が話せる環境に身を置き、フランスの生活リズムを忘れないよう努めました。そして19歳の時、再びパリに一人で渡ったのです」
特に留学生は周囲のフランス人や他の外国人とのコミュニケーションのために、言葉の問題でさまざまな苦労を経験する。
「電話が怖くて、ベルが鳴るたびにドキッとして居留守を使ったり、たまに取ると片言のフランス語で「ナルシマ ハ イマセン」とごまかしたりなんてことも!」
私(筆者)も約40年前にパリに来たが彼女の話は身に沁みて分る。当時夫が海外勤務で生まれたばかりの息子をパリで一人で育てていた時、郵便物で書類が来ると重要かどうか判断できずに、フランス人の友人に聞いても責任の問題なども含めて見る書類はいつも「ワカラナイ」で終わった。子連れで日本に帰ったことがあるが、パリに戻れば未解決の書類の山が待っているので憂鬱になったことを思い出す。もちろん笑い話のような楽しいエピソードも山ほどある。
「こんな出来事もありました。2000年の頃、カナダ人の持っているピアノの弾けるアパルトマンの4階に住んでいたのですが、朝5時頃、4階の別の部屋から火の手が上がりました。私は窓の脇に付いているトイを伝わり3階に滑り下りて、その部屋の窓を蹴って壊して中のカーテンを引っ張り、鼻と口にあてました。そのように煙から身を守っている間にも大声で近所の方たちを起こし、急いで消防車を呼んでもらって一命を取り留めました」
携帯電話を持ち歩いていない頃で、アパルトマンの住居人たちが命拾いをしたのは彼女のお転婆が役に立ったということだ。

南仏のフェスティバルで開かれた教会でのリサイタル


教会に響く割れんばかりの拍手とスタンディングオベーションに応えて
自分に嘘をつかない演奏をする
「イタリアのフィレンツェに住んでいた先生でロシア人のピアニストとの出会いや、サマーキャンプでヨーロッパ中を移動して音楽を貪欲に吸収しました。イモラにある中世のお城の音楽院は世界中から先生や生徒が集まる場所でした。ここの3年間は夜行列車で、パリとイモラ間を通いましたが、学生生活の中でも特に有意義な時間でした」。イタリア政府の援助により1年間の学費は6万円かかるのみですんだという。
「日本だったら一年で1千万円はかかるでしょう。学生に対してヨーロッパはインスピレーションの宝庫であるだけでなく、お金をかけなくとも素晴らしい音楽家と学べる機会を提供してくれる」と。将来性のある学生には国は惜しみなく援助をする。
「両親には『音楽と食べ物にはお金を使っていいよ』と言われていましたが、そうかといって年中レストランに行くわけにはいきませんので、大いに自炊をし料理の腕も大分上がりました」
つまり感性と肉体(健康)に対しての理解ある両親の言葉だ。彼女は2005年にフランス国立リヨン音楽大学院に入学した。フランスでは国立はパリとリヨンだけであり、その年はフランス中でたった3人のみ合格できたのだった。これが彼女の今後の演奏やピアノ教師などに大いに役立つキャリアとなっている。この期間にも多くのヨーロッパでのソロ・リサイタルや他の音楽家や交響楽団との共演がある。
ピアノコンサートの時に一番気をつけていること、大事なことは?と問うと「自分に嘘をつかない演奏をするよう、常に常に集中しています」と即答した。
「大事なことは、お客様へ楽譜から私が聴こえてくるものを忠実に届けたということですが、少しでもそこに邪険が入ったり、何か自分の意図するものと違うものが入ってこないよう、そして自分で造りあげてきたものが、緊張感の中で聴いてくださる方へ届くよう、ある意味常にコントロールをしています」
緊張感を持つけれど、体が硬くなっては表現へスムーズに繋がらないので、集中力と精神力でコンサートを作り上げていくのだ。
「1回のコンサートが終わるとフルマラソンを成し遂げたような疲労感がありますが、同時に次のコンサートが楽しみで仕方がないのです」

ナント北部のお城(Château de Bézyl)でのコンサート
ピアノという楽器を通してメッセージを伝える
2009年にフランス人の国家公務員と結婚、3年間ほど夫の仕事の赴任先であるニューカレドニアの首都ヌメアのニューカレドニア音楽院でピアノ教師として、また声楽科のクラスの伴奏者として仕事をしていた。ここでの生活と仕事は彼女にとって大変珍しい経験をもたらすことになったという。
「1892年に、600人前後の日本人がニューカレドニアのニッケル鉱山にて『契約労働者』として働らくため、移民会社の斡旋で移り住みました。1919年までに、なんと5575人にものぼる日本人移民がニューカレドニアで労働契約書のサインのもと働き、生活をしていたのです。私は初めてニューカレドニアの日系人の存在を知ったのですが、現在は日系5世がおり、名誉領事は日系2世の方です。私達が滞在していた2012年には、この重要な歴史的事件から120年ということで、日本人慰霊祭や日本にまつわる様々な催が行われ、私も働いていた音楽院に三味線奏者を日本からお呼びしてコンサートを企画するなど、今でも心に残る思い出に溢れている土地です。ニューカレドニアにはフランス人の政治犯の牢獄もあり、決して明るいイメージだけではありません。近隣のパプアニューギニアでリサイタルを開いたりと、3年間と短くも非常に内容の濃い滞在でした」
ニューカレドニアで男の子を出産している。子育てと仕事を両立させていたという。
「あの国では、音楽をやっていたからこそ色々な民族と出会う事ができたと思っています。ヨーロッパでしたら音楽院を終了すると、その後は『技術』をさらに磨き、その後どれだけコンサートを行うかという世界へ突入していきますが、カレドニアで得たことは生きる事・話す事という自然の五感の中に音が入ってきて、ピアノという楽器を通してメッセージを訴える思いが強くなったということです」
得意な曲は?と伺うと「リストです」と目を輝かした。
「彼は作曲家であり、ピアニストでしたが、『ソリスト』という現在のピアニストの形を作った人です。それまでの演奏スタイルといいますと教会やお城で行われる器楽合奏、ピアニストは歌手の伴奏や室内楽が常でしたので、当時としてはセンセーショナルな出来事だったのです。彼のファンの取り巻きは、まるで宗教家に心頭するような感じだったようです。リストと同時代のショパンは『バゲット(フランスパン)の様なもの』と表現されるほどピアニストにとって、ショパンの演奏は必要不可欠と言われています。今までは私にとって遠かったショパンも、ようやく彼の音楽を心で感じ取ることがで出来てきて、本当にここ最近、自分なりの解釈ができるようになってきました」
それはここまでの彼女のピアニストとしての音に対する姿勢と自信からであろう。現在、ソリスト・室内楽奏者としてヨーロッパ、日本を中心に精力的に演奏活動を続けている。
TOMOKO K. OBER(パリ在住/画家・ミレー友好協会パリ本部事務局長)