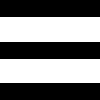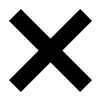大覚野(だいかくの)峠。中里介山の小説『大菩薩峠』の響きに似てかっこいい。一時存続が危ぶまれた「秋田100㌖チャレンジマラソン大会」は、仙北市角館から北秋田市鷹巣まで、これも存続が危ぶまれる秋田内陸線とほぼ並行して走る鉄人競技である。角館を発ち西木へ30㌖走ると標高582m、道のり15㎞の大覚野峠が走者を待つ。ここを越えてやっと中間地点50㌖が北秋田市阿仁。大覚野峠は秋田県を地理的にも文化的にも南北に分かつ。
峠の北側、マタギで有名な阿仁の病院に勤務していた昭和の末頃、「俺たちは昔、峠の向こう(南側)に憧れたものだ」と話す老人にお目にかかった。阿仁は江戸時代に鉱山で繁栄し平賀源内が技術指導に招かれもしたが、米もあまり取れない山岳地帯で何度も飢饉に見舞われた。一方の南側、横手盆地を中心とする角館から湯沢に至る広大な平野は米に恵まれ、ヤマセに悩む東の岩手から飢えた人々が命がけで和賀山塊を越えてきたという。「仙北が豊かな証拠は冬の祭りだ」とも老人は語っていた。祭りとは冬の小正月行事をさす。
その小正月行事の一つ、大覚野峠の真南、作家の西木正明が生まれた西木の「上桧木内の紙風船上げ」は2月10日である。平賀源内が佐竹北家の角館から阿仁鉱山へ向かう途次、熱気球を住民に伝授して始まったという。午後6時。幅3㍍、高さ6㍍の紙風船数個が夜空にゆらゆら舞う。材料は業務用和紙。ガス火で暖気が送られ膨らむと灯油を浸した下部の布玉に点火する。美人画や「祝古希」「五穀豊穣」「みんなの実家・門脇家」など図像が映え、放つと勢いよく上昇してゆく。途中ひっくり返ってしぼみ、布玉の火が燃え移り墜落炎上する風船もあり、冬でないと危ない。
2月15日、角館の南35㌖の横手へ「かまくら」見物に出かけた。市内各所に高さ3㍍超まで積み上げた雪に「プロの職人」が穴をうがち水神様の神棚を設けミカンなどお供えをする。かまくらの中で子らは「おざってたんせ」と雅な言葉で客を招き甘酒を振る舞い、「オー、ファンタステック!」などと異人客らを喜ばす。ライトアップされた横手城の広場にもかまくらは並ぶ。近くの「蛇の埼川原」に300人のボランティアが350㍍にわたって3500個作って灯をともす「ミニかまくら」も圧巻である。
2月10日の「紙風船」から「刈和野の大綱引き」と「大曲の綱引き」で狂奔し、角館の「火振り」は9月の曳山より、大曲の「ぼんでん(梵天)川渡り」は夏の全国花火競技会よりは大人しいものの、六郷のかまくら「竹打ち」で竹竿を叩き合う人々に異人客は「オー、クレージー!」と喜ぶ。画家の藤田嗣治は裏日本を巡る旅で「横手から大曲で乗り換え角館に冬の日を送った時が思い出に深い」と述べているが、湯沢、横手から角館、西木に至る南北35㎞で真冬の1週間、春の農作業を前に人々は魔物に憑かれる。といった話を肴に横手のレストラン『とぶ』で娘の舅姑と飲んだ湯沢の酒、両関『花邑』が実に美味だった。〈2025.3.8〉

阿仁スキー場のモンスターたち(樹氷)

上桧木内の紙風船上げ

夜空に舞う紙風船は平賀源内が伝授したとされる

角館の曳山祭り(9月)

大曲のぼんでん川渡り

横手城とかまくら

「おざってたんせ」と客に声をかけている

横手川の「蛇の埼川原」のミニかまくら