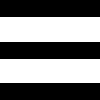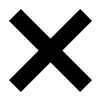紺屋今昔
名月の 花かと見えて 綿畠 芭蕉
江戸から明治にかけて寒冷地を除いた日本の農村で仲秋から晩秋に見られた月夜の光景です。
インド、エジプト、アフリカを原産とする木綿は紀元前から重要な衣料の素材繊維として広く用いられてきました。中国大陸から朝鮮半島を経て我が国に木綿の栽培技術がもたらされたのは意外に遅く、16世紀半ば、室町時代でした。大部分の衣料を麻布に頼っていた当時、保温性、吸湿性、柔軟性に秀でた新しい繊維の登場は、その後の日本人の衣生活をどれだけ豊かにしたか、現代の我々の想像以上の画期的な出来事でした。
綿作が全国的な広がりを見せた時と期を一にして、木綿を染めるための紺屋(藍染屋)がどんな小さな村にも町にも生まれました。現在の益子町にも、明治時代には6軒の紺屋が業を営んでいたと伝え聞いています。江戸中期から明治初期にかけては、日本人の用いる衣類の80%が藍で染められたと言われています。
藍染めの原料である最も良質な藍玉を生産した、阿波、蜂須賀藩25万石は、実質内容50万石以上と言われた程、藍が一国の経済を支える存在でありました。
藍はエジプト・インドといった古代文明の発祥地だけでなく、長い世界の歴史の歩みの中で、あらゆる民族の衣装を彩ってきた代表的な植物染料です。タデ科の植物「蓼藍」を原料とした日本の藍染め技法は弥生時代中期から始まったと考えられていますが、江戸時代の職人文化・町人文化の高揚が技術を飛躍的に高め、「ジャパンブルー」「広重ブルー」と世界中に賞賛される最も繊細な色として完成しました。現在でもこの時期の染色全般にわたる技法と色は、我々紺屋の目標です。藍の色は白に近い気品ある薄青から染め重ねることで濃い紺色までそれぞれの色相が得られます。江戸時代の色名帖には藍の濃淡の色名が記されています。色名は時代によって変化する場合もあるが17色の色を見分け、染め分け、使い分けたとすれば、先人達の技術レベルの高さ、眼の確かさには驚嘆するばかりです。いづれにせよ日本人ほど藍の豊富な色相を生かしきった民族を私は外に知りません。明治23年に来日したラフカディオ・ハーン(日本名 小泉八雲)は日本の印象記を残しています。「この国は大気全体が、心持ち青味を帯びて異常なほど澄み渡っている。青い屋根の下の家も小さく、青い暖簾をさげた店も小さく、青い着物を着て笑っている人も小さいのだった。」ハーンにとって日本は神秘なブルーに満ちた国だったのです。
盛んだった藍染めも明治時代後半には合成染料の普及や紡績、自動織機の発達などに代表される、所謂産業革命の波に洗われ、急速に衰退していきました。そのため大正・昭和期には数多くの紺屋が廃業に追い込まれていきました。
現在、紺屋を取り巻く状況は、益々厳しさを増しています。栃木県内で同業者は2軒だけになってしまいました。ハーバード大学の社会学者タマラ教授の予測があります。「現在世界的に伝統工芸は非常に厳しい状況下にある。しかし人類は地球的規模の環境破壊の反省から、今後『自然回帰・土に帰ろう』の潮流が起こって来るだろう。伝統工芸の見直される時は必ず来る」
現代における藍染めの持つ可能性を探りながら「益子の紺屋」として前に進む以外の道はないと思っています。







(文:日下田 正/下野手仕事会40周年記念誌『下野手仕事会四十年之軌跡』P64-65より)