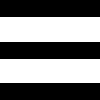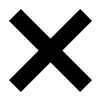下野手仕事展
栃木県内の伝統工芸品の職人たちの集まり、下野手仕事会による「下野手仕事展」が栃木県立博物館(宇都宮市睦町)で開かれた。2022年11月中旬の6日間、博物館1階のエントランスホールにさまざまな伝統工芸品、民芸品が並び、展示販売だけでなく、会員による実演もあり、大勢の来場者でにぎわった。下野手仕事会の会員は現在35名。木工、織物、陶芸、絵画などさまざまな分野の手仕事を手掛ける職人がそろう。
最終日の日曜日に紙漉(す)きを実演した烏山和紙の福田長弘さん(那須烏山市)。来館した子どもたちに説明したり、体験させたりする場面もあった。
「手仕事展は毎回参加していますが、現場での実演は初めて」
大きな紙を漉く場所は取れないので水と原料の繊維が入ったたらいで和紙のはがきを作っていく。竹を編んだ漉き簀(す)と木枠「桁(けた)」を使い、コウゾの木の皮を細かくして柔らかくした繊維をすくうが、直前にはトロロアオイの根から採った無色透明の粘液を入れる。福田さんは「紙を固めるためのものと思われがちですが、実はすぐに粘りはなくなってしまいます。これは原料を沈殿しにくくし、原料の濃度を一定にするためのものです」と解説。漉いた後は桁から外して、紙の水分を切っていく。「この時点では水の含有量が多いので、ここでは十分に厚みを持たせないと出来上がったときにティッシュペーパーのような薄さになってしまいます」と説明した。
県内唯一となった和紙作りを引き継いでいる福田さんは「ものが出来上がったときの喜びが一番。自分がこだわって作るというよりも、使ってもらう人の用途にぴたっと合ったときがいいなと思うし、用途によって作る和紙も準備の仕方から違ってきます。書くための紙だけではなく、家の内装、空間造りのポイントに和紙を使いたいという注文もあるし、個人の家の障子から公共施設や商業スペースまで用途は多様。それに合わせて作っていくことが楽しさでもあり、苦しさでもあります」と和紙作りの醍醐味を語った。

創立50周年を見据えて
下野手仕事会は1974(昭和49)年に発足したが、鼈甲(べっこう)細工の田中昭二さん(佐野市)は87歳で、初期からのメンバー。「創立の翌年あたりに入ったのかな。最初の会長さんからお付き合いさせていただいている。鼈甲細工は親父が始めて、兄弟で助けてきた。あのころは品物を作れば売れる時代だった」と当時を振り返った。2024年には手仕事会50周年を迎えるが、「元気でいられるかな」と豪快に笑った。
地域の独自性がみられるのも伝統工芸品の特徴だ。
日光下駄の山本政史さん(日光市)は実演をしながら「真竹のタケノコの皮で編むが、これが難しい。両脇を折って表向きで編んでいかないといけない。布やワラなら表も裏もない。材料、作り方に伝統がある」と説明する。日光下駄は下駄の台木に草履を縫い合わせた履物で、日光東照宮を参拝する殿様だけが履いたもの。伝統の材料、技法を大切にする一方で「今は時代に合うものを作るように変わらないと受け入れてもらえない」と時代の要求にも応え、洋服に合うコーディネートなどアレンジも施している。
野州てんまりの赤池民子さん(宇都宮市)と長谷川和子さん(宇都宮市)はともに故中山春枝さんに師事し、その伝統を守ってきた。2人は「発泡スチロールを使わず、カイコが繭を作った後に残る毛羽を丸めて作っていきます」と説明。また、柄も栃木県ゆかりの草花などをモチーフにし、栃木らしさを大切にしている。

下野手仕事会発足当初から続く恒例の手仕事展は今回が48回目で、県立博物館に会場を移してからは4回目となる。小砂焼の陶芸家である藤田眞一会長(那珂川町)は「多くの人に見てもらい、知ってもらえる機会。手で作る品物の良さ、しっかりした物だということを認めてもらわないといけない。子どもたちにも触ってもらったり、体験してもらったりする機会になれば」と強調した。伝統工芸品は後継者難が問題となっているものもあるが、「最近、話を聞きたいという中学生や高校生もいるし、伝統工芸品の良さを分かってくれる若者もいる。継続できる可能性は秘めている。50年近く続けてきたので作り手も時代を反映している。今の時代に求められる物も作っていかないと」と話し、まもなく迎える手仕事会50周年に向けて、さらなる発展への意気込みを示した。